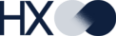メタバースにいま足りないもの ―「メタコミュニケーション®」の実現のために―(前編)
2023年11月09日

メタバースは、指数関数的な伸びが予想されるものの、実際の普及は「まだまだこれから」の状況にある中、Apple社も注目するSpatial Computing(空間コンピューティング)は、普及に「一役買う」可能性がある。
本コラムでは、メタバースの次のあり方について「Spatial Computing」というApple社の視線と、「失われたWell-beingを取り戻す」というRidgelinezの視線を取り上げ、東京大学の認知神経学者である渡辺正峰(まさたか)氏からの示唆を踏まえて考察した内容を前後編にわたって紹介する。
前編では、いわゆる「メタバース市場」がどのように考えられているか、未来予測と現在地をレビューする。そのうえでApple社が据える「メタバースの『次の一手』」について考察のうえ、Ridgelinezなりの「メタバース像」をご提示する。
目次
1. メタバースの現在地
「メタバース」という言葉の広がりに比べ、「メタバースが有用だ、楽しい」という声はどれほど挙がっているだろうか。
(1)指数関数的に「伸びる市場」という眼差し
メタバース市場は世界市場を見ても、国内市場を見ても、「伸びる市場」であると見られてきた。
例えば、「メタバースの世界市場は2021年に4兆2,640億円だったものが2030年には78兆8,705億円まで拡大すると予想されている(※1)」ように、100兆円級の規模になる可能性が示されている。
この「2030年時点で100兆円級規模」というのは、「半導体市場は、デジタル革命の進展に伴い今後も右肩上がりで成長(2030年約100兆円)(※2)」と、半導体市場で予測される規模感でもあるため、メタバース市場が半導体市場に比肩する市場となることを示唆しているとも言える。
世界市場と同様に、国内市場においても「2021年度の国内メタバース市場規模は744億円と推計され、2022年度は前年度比245.2%の1,825億円まで大きく成長すると見込まれた。(中略)2026年度には市場規模が1兆円を超えるものと推測する。(※3)」というように、指数関数的な規模伸長が予測されている。
(2)繁栄や成長は「これから」
一方、「【だからメタバースは「使えない」】メタバース事業化「失敗」が9割、オワコン懸念を払拭する2つのポイント」と銘打たれた日経クロステックの記事(※4)は、「メタバースが振るわない。華々しく発表したものの利⽤が低迷するメタバースが続出。事業化の停滞や中⽌に追い込まれた企業は9割超に達するとの調査もある」という書き出しで始まっている。
メタバースの現在地を総括すると、「輝かしい繁栄が期待されながらも、足元では「確かな成長」を実感できない状況にあるのが『メタバース市場』の現状である」と言えるのかもしれない。
しかしながら、メタバースはまだ黎明期の位置づけである、メタバースは「これから」の存在であると、Ridgelinezは考えている。
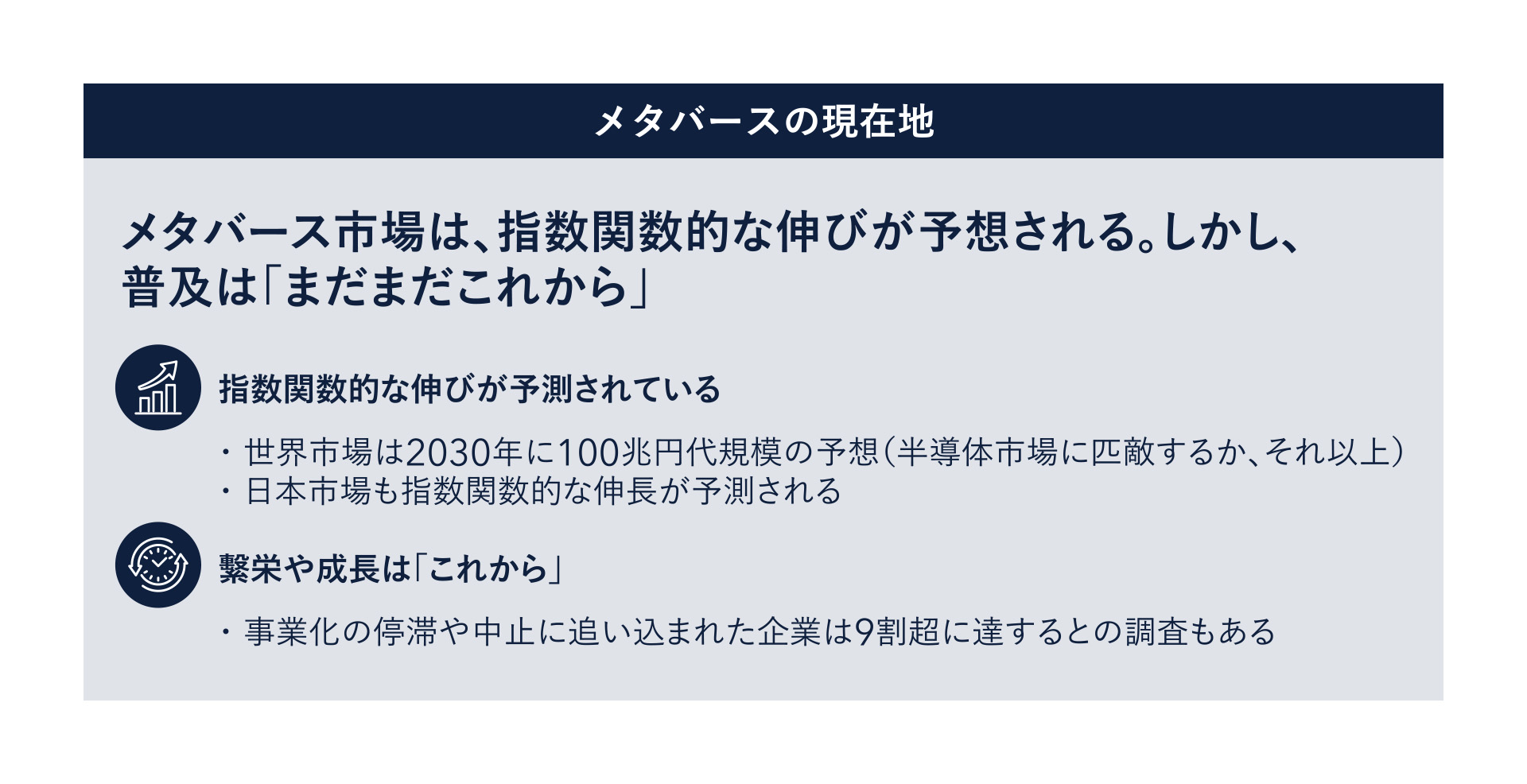 【図1】メタバースの現在地
【図1】メタバースの現在地
(※1) 総務省 令和4年版情報通信白書
(※2) 経済産業省 2021年6月 半導体戦略(概略)
(※3) 矢野経済研究所2022 メタバースの法人向け市場動向と展望
(※4) 日経クロステック「メタバース事業化「失敗」が9割、オワコン懸念を払拭する2つのポイント」
2. Appleの視線、「Spatial Computing」
このような中、2023年6月、Apple社はWWDC(Worldwide Developers Conference, 世界開発者会議)(※5)において新製品「Vision Pro」を発表した(※6)。発表に際してCEOティム・クックは「Spatial Computing(空間コンピューティング)」という言葉をもって、以下のように、同製品の特徴を市場に訴求した(※7)。
「今日はコンピュータの歴史にとって新たな時代の幕開けとなる記念すべき日となるだろう。Macがパーソナルコンピューティングを、iPhoneがモバイルコンピューティングを実現したように、Vision Proは我々を空間コンピューティングの世界へと導く」
(Apple社CEO ティム・クック)
そして、ティム・クックは、この新たなデバイスを紹介するにあたって「メタバース」という言葉を使わなかった。
(※5)Apple Inc. プレスリリース「AppleのWorldwide Developers Conference 、6月5日(日本時間6月6日)に開幕」
(※6)Apple Inc. プレスリリース「Apple Vision Proが登場 — Appleが開発した初の空間コンピュータ」
(※7)IT Leaders 2023年6月6日
(1) Apple社が着眼した「Spatial Computing」のこれまで
Spatial Computing(空間コンピューティング)という言葉の起源は、2003年に発表された「MIT Media Lab」のSimon Greenwoldによる論文にある(※8)。同論文では「Spatial Computing」を「マシンが現実の物体や空間への参照を保持、および、操作することを通じた、マシンと人間の間の相互作用である」と定義している(原文:“Spatial computing is human interaction with a machine in which the machine retains and manipulates referents to real objects and spaces”)。
Spatial Computingにかかる実証実験が世に知られるようになったのは、上記の論文の発表から十数年の時を経た、2015年前後であった。Google社のGoogle GlassやMicrosoft社のHoloLens(※9)に代表される「ウェアラブルデバイス」が登場したタイミングであった。同時点では、例えば、設計工程で製作された3DCADデータと、製造工程で作られた製品を重ね合わせた、異常箇所の検知や作業効率化などへの活用が図られていた。
以降はやや「沈静化」した状態にあった。実証実験から一定の有用性が確認されたものの、コンテンツ作成やメンテナンスにかかるコストに得られる収益が見合わず、ビジネスとしては育たなかったためである。また、長時間デバイスを着用する必要があったことも一因であったと考えられる。
(※8) Greenwold, Simon. “Spatial Computing” 2003
(※9)マイクロソフトコーポレーション プレスリリース「Microsoft HoloLens のプレオーダーを 12 月 2 日(金)より開始」
(2) Apple社がVision Proから「観ている」未来
2023年9月12日、Apple社はiphoneとApple Watchの新製品を発表した。iPhone 15/ProにはVision Proの「空間ビデオ機能」が搭載され、Apple Watchのジェスチャー操作機能が搭載された(※10)。
注目したいのは後者のジェスチャー機能である。Apple Watchをつけている腕でジェスチャーをすることで、「画面を触らずに」アプリケーションの操作ができるようになるのだ。
当該機能に関連して着眼したいのは、米カーネギーメロン大学で「Human-Computer Interaction(人とコンピュータの相互作用)」を研究するクリス・ハリソン氏の研究である。
同氏は、2016年時点でジェスチャー機能を搭載したスマートウォッチに関する研究結果を発表していた(※11)。また、指導した卒業生の中には、現在Appleで研究開発を担うメンバーも含まれ、やはり「Spatial computing」がキーワードの1つとして挙げられている。
このことから、クリス・ハリソン氏の研究成果を追うことは、Apple社が描くSpatial Computingを考察するための「補助線」となり得ると考えられる。
例えば、研究成果の中には、以下が含まれる。
-
- 皮膚そのもののタッチディスプレイ化(Skinput)(※12)
- 料理、歯磨き、運動、ドアの開け閉めなど、生活の動きの検出と連動(Crowd-AI Camera)(※13)
- 視線と手首の動きでスマートフォンを操作できるシステム(EyeMU)(※14)
上記の3については、Vision Proにおいても同様の機能が搭載されている。
同製品の紹介サイトには、「空間体験の操作を実現するため、Apple Vision Proではユーザーの目と手、声によりコントロールする世界初の入力操作システムを採用しています。視線を向けるだけでアプリをブラウズできるほか、項目をつまむようにタップして選択したり、手首を上下左右にさっと動かしてスクロールしたり、声で文字を入力することも可能になります」と紹介されている。
このように、Apple社は「感覚(センサー)機能」を拡張する技術をもって「モノ(機械)」と「ヒト」の連動、すなわち「IoTの質」を高めようとしている。
このことは、身体をもってIoTを実現するような「空間情報をもとにした身体拡張(Human Computer Interaction)」を進めているとも言えるのではないか。そして直近の新製品の機能動向から、「Spatial Computing」を通じた「現実世界の仮想現実化」、つまり「『現実世界』を、『従前の仮想現実の世界(これまで人々が夢みてきた「魔法の」世界)』に近づける」という姿勢が窺えるのではないか。
(※10)Apple Inc. プレスリリース「Apple、iPhone 15 ProとiPhone 15 Pro Maxを発表」、「Apple、先進的な新しいApple Watch Series 9を発表」
(※11)Chris Harrison's Website「ViBand: Bio-Acoustic Sensing Using Commodity Smartwatch Accelerometers」
(※12)Chris Harrison's Website「Skinput: Appropriating the Body as an Input Surface」
(※13)Chris Harrison's Website「Crowd-AI Camera Sensing in the Real World」
(※14)Carnegie Mellon University School of Computer Science「Your Eyes Control Your Smartphone With CMU's New Gaze-Tracking Tool」
(3) 「身体の拡張」への熱い視線
この「現実世界の仮想現実化」というキーワードで筆者が想起するのは、今年7月に第169回芥川賞を受賞した「ハンチバック」の作者、市川沙央氏のことである。
彼女は筋力などが低下する筋疾患の「先天性ミオパチー」という難病を患っているため、「紙の本を読む」という行為自体が難しい。彼女は作中で「読書バリアフリー」を謳っていた(※15)。
受賞作には、このような記述がある。
「厚みが3、4センチはある本を両手で押さえて没頭する読書は、他のどんな行為よりも背骨に負荷をかける。私は紙の本を憎んでいた。目が見えること、本が持てること、ページがめくれること、読書姿勢が保てること、書店へ自由に買いに行けること、――5つの健常性を満たすことを要求する読書文化のマチズモ(※16)を憎んでいた。その特権性に気づかない『本好き』たちの無知な傲慢(ごうまん)さを憎んでいた」
「紙の匂いが、ページをめくる感触が、左手の中で減っていく残ページの緊張感が、などと文化的な香りのする言い回しを燻(くゆ)らせていれば済む健常者は呑気(のんき)でいい」
(以上、市川沙央「ハンチバック」より引用)
いまApple社が進めようとしている、IoTの質を高めることは、市川沙央氏のように「現実世界に、容易に改善しがたい『不』を抱える方」の「不」を取り除く、「生きやすさ」のための側面もあるのではないだろうか。
例えば、海外の先端研究に目を向ければ、脳とコンピュータをつなぐ技術である「ブレイン・マシン・インターフェース(BMI)」を使い、脳卒中患者の方が18年ぶりに自らの「声」を取り戻した事例や、脳波からコンピュータを操作する技術の事例が報道されている(※17)。
また、国内にも「(身体的な理由だけでなく、精神的な理由を含め)社会とのつながりを持つことが難しく、孤独と闘っている人たち」が分身ロボットOrihimeを操作して接客する「分身ロボットカフェ」も近年登場している。
このように、「現実世界に、容易に改善し難い『不』を抱える方」の「不」を取り除き、「生きやすさ」を手にする、という方向での「身体の拡張」に熱い視線が注がれている。
なお、Apple社は開発者にディベロッパーツールを公開している(※18)。現実を従前の仮想現実のような世界に変えていくような「Spatial Computing」の世界をオープンイノベーション的に拡張しようとしている状況と言える。
Appleはメタバースの「伸び」を実現するEnabler(実現する仕組み)として「Spatial Computing」に着眼している状況にあると、Ridgelinezは考えている。
(※15)朝日新聞「命綱の本が紙クズに変わる時 芥川賞「ハンチバック」が問うマチズモ」
(※16) マチズモ:machismo。男っぽさ。 誇示された力。 男性優位主義。
(※17)日経新聞「イタリアの名門、脳科学で脚光 「念力」でパソコン操作」
(※18)Apple Inc. プレスリリース「Apple Vision Proの空間体験を生み出すデベロッパツールの提供を開始」
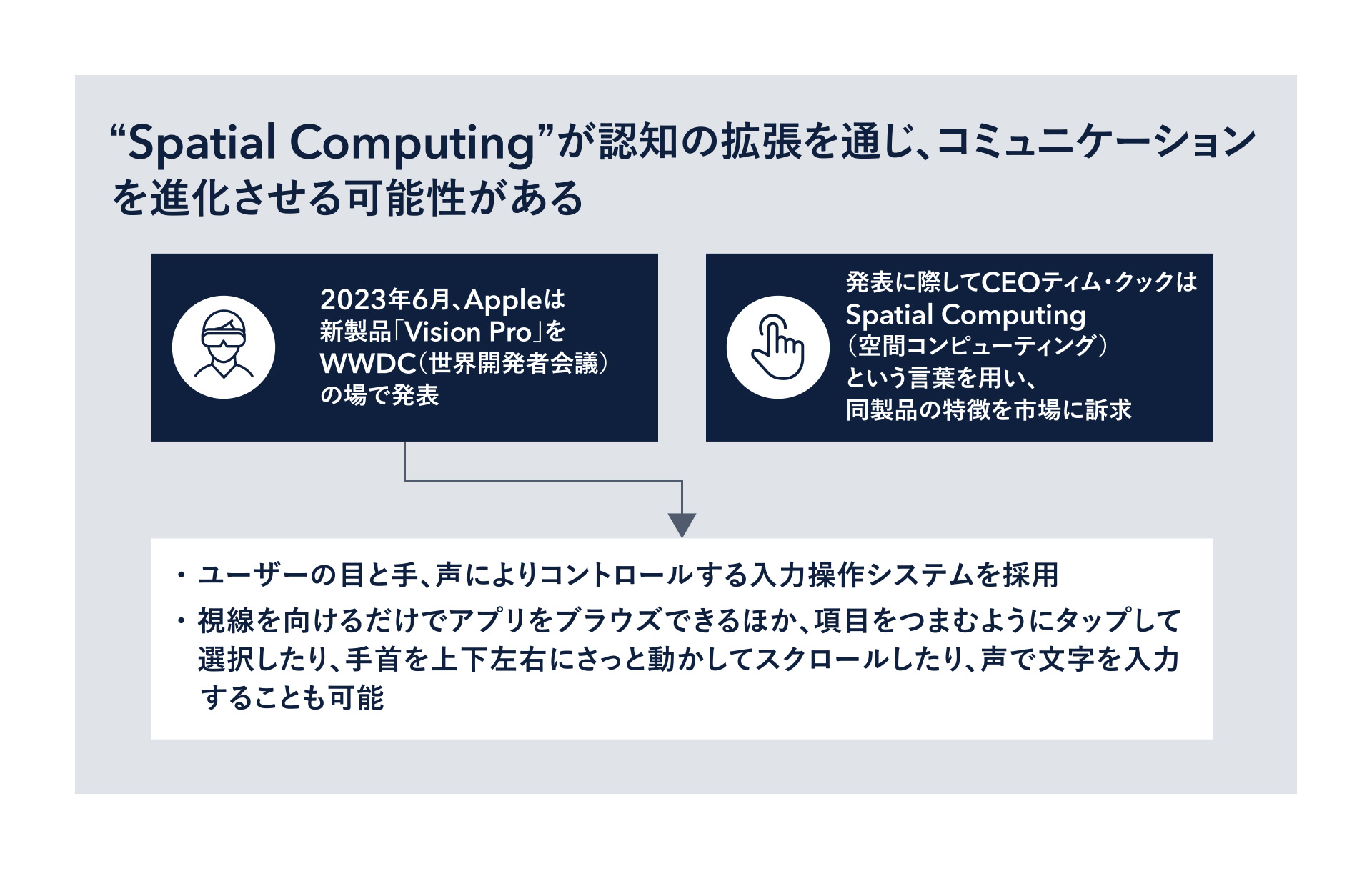 【図2】Appleの視線 “Spatial Computing”
【図2】Appleの視線 “Spatial Computing”
3. Ridgelinezの視線、「失われたウェルビーイング(Well-being)を取り戻す」
Appleが従来「メタバース」と呼ばれてきた「コンピュータの中に構築された3次元の仮想空間で、専用のゴーグルやアバターを使って接続する場」を、「Spatial Computing」によって拡張/越境していこうとしている中、我々Ridgelinezは「メタバース」の概念自体に問いかけを発している。
Ridgelinezが捉える「メタバース」
PRESIDENT 2023年11.3号の記事で、Ridgelinezシニアアドバイザー 佐藤浩之は、以下のように語っている。
「遠く離れている空間とつながっている感じがしたら、それはもうメタバースです」
「(新卒でNTT入社後、約25年間、通信業界におけるテクノロジーの進化を最前線で見てきた中で)一貫しているのは、コミュニケーションについて考え続けてきたこと。従来の通信は電話もインターネットも、ほとんどが言語のやり取りでした。メタバースの出現は、その流れを大きく変えた。VR(仮想現実)やAR(拡張現実)といったテクノロジーを取り入れることで、体験や感情など非言語コミュニケーションも可能になったのです」
「メタバースは『失われたウェルビーイングを取り戻す空間』。例えば寝たきりの生活を余儀なくされた人も、メタバース上で大自然の空気を体感できるかもしれない。そんな仮説を立て、研究を続けてきた」
我々Ridgelinezは、「コミュニケーション」をキーワードに、「メタバース」という概念の持つ世界観を捉え直そうとしている。
同時に「なぜ『コンピュータの中に構築された3次元の仮想空間で、専用のゴーグルやアバターを使って接続する場』が存在するだけでは、メタバースたり得ないのか」という「問い」についても考察を深めている。
そして前述の「問い」を紐解くヒントは、認知神経科学を専門とする東京大学准教授である渡辺正峰(まさたか)氏の用いる、
「感覚意識体験(クオリア)」という言葉にあるのではないかと考えている。
ここまで、メタバースの次のあり方について、「Spatial Computing」というApple社の視線と、「失われたWell-beingを取り戻す」というRidgelinezの視線を取り上げ、考察してきた。
後編では渡辺氏の主張の概要と、Ridgelinezとの対談、そして本コラムの帰結としての「メタバースにいま足りないもの」についての我々なりの「解」を提示する。
執筆者
- 遠藤 泰治Manager
※所属・役職は掲載時点のものです。