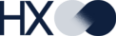デジタル型産業システムのオープン&クローズ戦略
2021年02月17日

オープン&クローズ戦略とは、製品やシステム、サービスを、「他社に公開するオープン領域」と「秘匿して利益の源泉にするクローズ領域」とに分け、エコシステムとして共存する仕組みを作る戦略思想のことである。当戦略は需要と供給の同時拡大を可能にし、2020年代にはサイバー空間とフィジカル空間を跨ぐ産業システムの全域へ広がるであろう。
本コラムでは、1980年代パソコンからのデジタル産業の歴史を観察してオープン・アーキテクキチャーを「背後に秘匿領域・差異化領域を持ったうえで共生的につながる産業システムの設計思想」と再定義する。そして、それによってゲームチェンジが起きるメカニズムと、日本企業がゲームチェンジに対応するためにとるべきであったオープン&クローズ戦略について分析する。
1. オープン&クローズ戦略とは何か
オープン&クローズ戦略とは、製品やシステムあるいはサービスを、「他社に公開するオープン領域」と「秘匿して利益の源泉にするクローズ領域」とに分け、2つがエコシステムとして共存する仕組みを作る戦略思想のことである。
最近ではこれがさらに拡張され、互いにつながる企業が刺激し合って成長する共生型エコシステムの設計フレームワークとして使われるようになった。デジタル化が進んでオープン・アーキテクチャーへ転換する産業システムの中で、市場拡大(需要)と生産拡大(供給)を同時実現させる仕組みの設計思想となったのである。
オープン&クローズ戦略が需要と供給の同時拡大を可能にする背景として3つの理由が挙げられる。
- 第一に、それぞれの企業がつながって互いに刺激し合えばネットワーク効果が生まれ、市場が拡大するからである。
- 第二に、企業あるいは国がそれぞれ得意とする専門領域に特化してイノベーションを起こすだけで生産性が高まり、しかもこれがネットワーク効果によって増幅されるからである。
- 第三に、たとえ個々の企業や国の投資が少なくても、エコシステム全体としてなら巨額投資となり、規模の経済と範囲の経済によって収益も生産性もさらに増大するからである。
このような経済効果に着目した人々が、オープン・アーキテクチャーへ転換したすべての産業にオープン&クローズ戦略を取り込み始めた。現在ではソフトウェアやデータ、ネット通販、クラウドはもとより、インダストリー4.0(注1)のような国家プロジェクトへも広がる。オープン&クローズ戦略は2020年代にはサイバー空間とフィジカル空間を跨ぐ産業システム(Cyber Physical System)(注2)の全域へ広がるであろう。
注1:製造業におけるオートメーション化およびデータ化・コンピュータ化を目指す昨今の技術的コンセプト。元々はドイツ政府が産官学連携で進めた国家プロジェクトで第4次産業革命とも呼ばれる。Cyber Physical System、モノのインターネット、クラウドコンピューティング、コグニティブコンピューティングなどが含まれる。
注2:実世界に対するセンシング(データ)とコンピューティング(計算、意味理解)、それに基づくアクチュエーション(制御、フィードバック)を基本要素として、実世界(人、モノ、環境)とICTが密に結合・協働する相互連関の仕組み。
2. オープン・アーキテクチャーを定義し直す
アカデミアが語るオープン・アーキテクチャーとは、製品やシステムを構成するそれぞれのモジュールの役割分担を事前に決め、モジュール相互の連携とつながり方のルールも事前に決めて公開し、システム全体を独立したモジュールの組み合わせで表現することであった。
しかし、これは言葉の定義であり、つながるルールの公開やモジュールの組み合わせと経済成長(収穫逓増)との関係、企業収益との関係をここから導き出すことはできない。
オープン・アーキテクチャーが最初に現れた1980年代のパソコン産業でこれを語れば、個々の企業(当時のスタートアップ)は、パソコンという完成品を構成する技術のごく一部しか持っていない。したがって分業の単位としての企業は、それぞれ得意な技術モジュールを持ち寄ってつながらなければパソコン産業が生まれない。
ここで営利企業としての企業がビジネスチャンスを求めてパソコン産業へつながるには、データバスの通信プロトコルとインターフェイスが公正なルールで決められ、オープンなルールとして広く共有されていなければならない。しかし、これだけでは不十分である。リスクをとって自律的に投資するには、そのうえでさらにそれぞれの技術モジュールが所有権や特許権、営業秘密などによって守られたうえでのつながりでなければならない。
この2つがビジネス制度として保証されることによって初めて、イノベーティブな企業がビジネスチャンスを求めてつながり、リスクをとって投資しながら産業を発展させる。そもそも秘匿領域・差異化(クローズ領域)を語らず、オープン化だけを語る牧歌的な市場へ投資する人はいない。
1980年代から次々に現れたハードディスク、CD-ROM、半導体メモリー、インターネット、携帯電話、スマートフォン、そして現在のクラウドなど、オープン・アーキテクチャーと呼ばれるデジタル型の製品産業を観察すると、例外なくオープン領域とクローズ領域が共存するエコシステム型になっていた。
したがって本コラムでは、オープン・アーキテクチャーを「背後に秘匿領域・差異化領域(クローズ)を持ったうえで共生的につながる産業システムの設計思想」と定義し直したい。デジタル化が進む2020年代にはオープン・アーキテクチャーがほぼすべての産業領域へ広がる。したがって次々にゲームチェンジが起きる。自動車産業はもとより機能デバイス産業であっても、さらには工場などの生産システムであっても決して例外ではない。
3. 日本のオープン・アーキテクチャー化とオープン&クローズ戦略
我々が1990年代の後半から何度も経験したのは、液晶テレビ、CD-ROM/DVD、インターネット、携帯電話、LED照明、リチウムイオン電池、半導体、さらにはEMS(Electronics Manufacturing Service:受託製造)などモノづくりシステムがオープン・アーキテクチャーへ転換してゲームチェンジが起きるタイミングから、日本企業が例外なく市場撤退を繰り返す事実であった。
もし2020年代にオープン・アーキテクチャーが多くの産業へ広がり、ゲームチェンジが起きるのであれば、我々は今からどのような手を打っておくべきなのだろうか? これを語る前に、まずゲームチェンジが起きるメカニズムを理解しておきたい。
1990年代に急成長したエレクトロニクス産業を詳細に観察すると、いずれの製品産業もオープン領域を経由したつながりによる共生的なエコシステムになっており、互いにつながり合うことによって企業内に閉じたモノづくりより遥かに強大な経済効果を作り出していた。
例えば、オープン・アーキテクチャーのクラウド環境で急成長する現在のAmazonと1980年代のパソコン環境で成長するハードディスクは全く同じメカニズムで成長していたのである。さらには1990年代から急成長する鴻海(Foxconn、世界最大のEMS)も携帯電話も、そしてCD-ROMやDVDも、現在のAmazonと全く同じメカニズムで成長していた。
これを構造化して図1に示す。上に挙げた製品の成長には、確かにコンポーネント単体のイノベーションとアーキテクチャル・イノベーションの2つが貢献していた。しかし、互いにつながり合うことによって生まれるアーキテクチャル・イノベーションの効果の方が、企業内に閉じたモノづくりによる経済効果より遥かに強大である。この強大な経済効果がゲームチェンジを引き起こしていたのである。
我々は自社とパートナーとのつながりによって生まれる強大な経済効果に気が付かなかった。ハードディスクやDVDが現在のAmazonと同じメカニズムで成長することなど考えたこともなかった。しかし実は、我が国のエレクトロニクス産業が何度も市場撤退への道を歩んだ背景がここにあったのである。
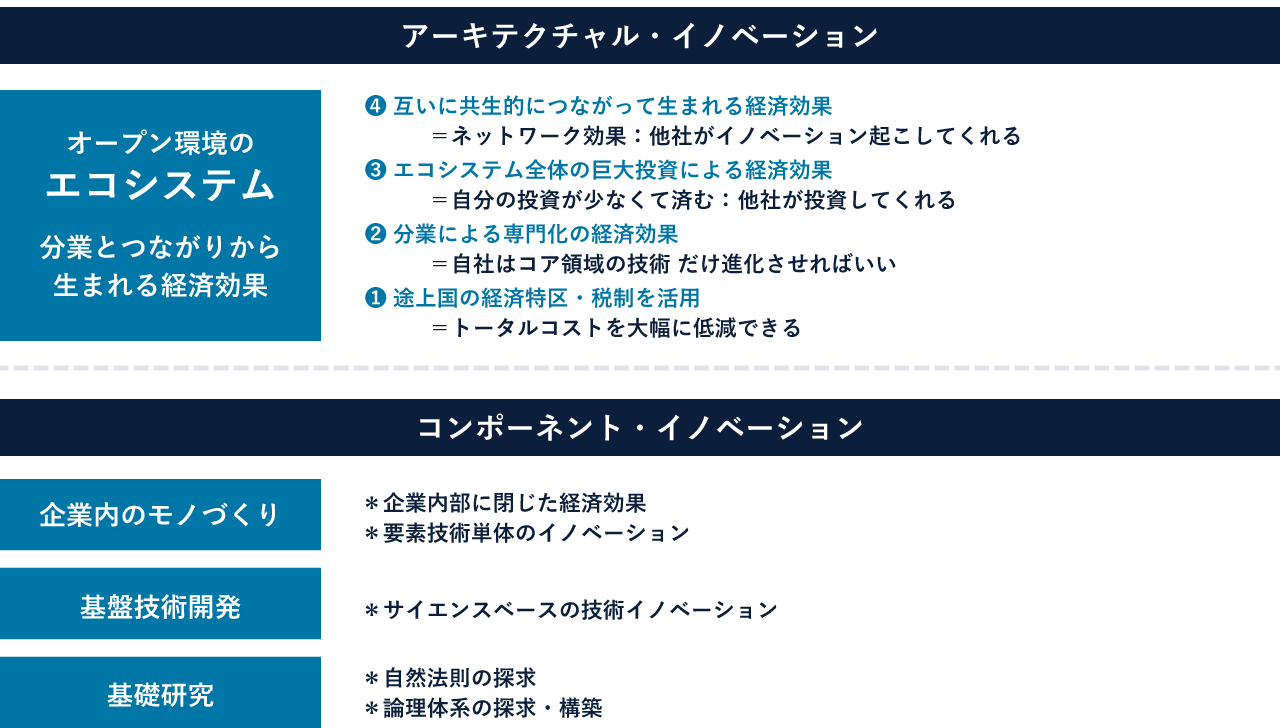
図1 つながる経済から生まれる強大な経済効果
強大な経済効果を自社・自国へ引き寄せなければ、図1のアーキテクチャル・イノベーションが引き起こすゲームチェンジに対応できない。後知恵でこれを語れば、我々に必要だったのは以下の3点である。
- 第一に、オープン&クローズの戦略思想でオープン・アーキテクチャーのエコシステム構造を自社優位に事前設計すること。
- 第二に、オープン&クローズ戦略で自社とエコシステム・パートナーとのつながりを自社優位に事前設計すること。
- 第三に、オープン・アーキテクチャーのエコシステムの中でつながりによって生まれる図1の①から④の経済効果をオープン&クローズ戦略で自社へ引き寄せる仕組みを構築すること。
4. 2020年代のデジタル経済に向けて
デジタル化が浸透する2020年代に多くの産業領域がオープン・アーキテクチャーへ転換し、図1の①からの④の強大な経済効果が至る所に現れる。また、これまで無かった、さらに新しい経済効果が、これまでのフィジカル空間ではなく、我々が未経験のサイバー空間に現れる。2020年代の日本企業はこれまで誰も経験しなかった経済環境に置かれるのである。
そこで今後は、日本企業が直面する諸問題を解説し、2020年代のデジタル経済へ漕ぎ出すためのコンパスと地図を描いてみたい。
執筆者
- 小川 紘一東京大学未来ビジョン研究センター シニアリサーチャー
Ridgelinez シニアアドバイザー
※所属・役職は掲載時点のものです